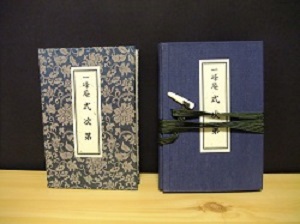手もと供養・観音経
私は墓・仏壇の必要性を問われたとき、強いて必要でないことをお話しし、ご不幸があったときに
備えて、例えば九谷焼とか備前焼とかの手のひらに乗るくらいの器を買っておいてください。
骨あげのときはその器に少しのお骨を入れて、あとは斎場で処分してもらって下さい。
愛しい人、大切な人を冷たい土の中に入れるよりも、故人の写真立ての横に小さなおリンと共に
手元に置かれ、手を合わせて「ありがとう」と言ってください。
何年後・何十年後に、いくつかに増えて埋葬されるのなら公営・民間の共同墓地をすすめています。
また、本来の仏壇は宗派の御本尊を安置する処であって、置く置かないはご自由です・・・
と答えています。
遺骨埋葬のこだわりもあと十年、二十年もすれば変化し、簡素化されるのでは?
当然、仏式葬儀の必要性も薄れるでしょう。
先日、あるご婦人から
「主人が最後を迎える数日前、あなた様にご相談させていただきました。
そのとき、気に入られた小さな器を買ってきて、その器にご遺骨を入れてもらって下さい。
それ以外のご遺骨は斎場で処分してもらってください。
持ち帰られたご遺骨を思いでの写真などと一緒に安置してくださいね。とおっしゃっいました。
葬儀の当日、娘が買ってきた小さな可愛い器に入れて持ち帰り、写真立ての横に置いています。
お鈴も可愛いのを買ってきてお父さんと声掛けして手を合わせています。
お墓、戒名、年回忌、お仏壇にもこだわらなくてもいい。お手元で供養してください。
と、あなた様からお聞きして安堵しております。ありがとうございました」
との言葉をいただきました。
*「手元供養」を検索してください。飾り台等、参考になると思います
仏式葬儀にこだわるも良し。今までの風習にこだわるも良し。こだわりから解き放されるも良し。
頑なに葬儀は仏式。という坊主が居るとするなら、もはや、坊主ではない・・・間違いでしょうか?
「見えなくても花を供えたい。食べなくても美味しいものを供えたい。聞こえなくても話したい。
見えざる者えの真心は美しい」
この純粋な心に、小賢しい説法は要らない。
手元にある思い出にそっと、手を合わせるだけでいい。
私たち夫婦は2021年に金婚式を迎えます。
それを機に大阪府箕面市の公営墓地に埋葬している両親の遺骨を小さな骨壺に入れ替えて
持ち帰り、私の彫刻した仏像の傍に置くことにしました。
そして、大阪市天王寺区の四天王寺四天王寺講堂に安置されている、
総高約6mの阿弥陀如来坐像の台座下に阿弥陀如来のプレートを奉納することにしています。
この仏像の制作に、彫刻教室の先生も携わっておられました。

お経は何を唱えればいいのでしょう?と尋ねられたら、観音経をおすすめしています。
漢文経典の中で最もポピュラーなのは「般若心経」です。
それに次いで読経されるのが「観音経」でしょう。
観音経の中の「偈」の部分は、般若心経と並んで写経のお手本として親しまれたいます。
「観音経」は何処にいても どんな時にでも わたしたちに普く門を開かれ「普門」、
さまざまな災難 そして悩み苦しみを三十三の姿(相)をもって救いくださる観世音菩薩の
はたらきをのべた章「品」で妙法蓮華経の「第二十五番目」のものです。正しくは
「妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二五」(みょうほうれんげきょうかんぜおんぼさつふもんぼんだいにじゅうご)
です。西国三十三か所参りは観音様が三十三の姿(相)をもって救いくださるという信仰に
由来するものです。
「妙法蓮華経(法華経)」とは、わたしたちの知恵の及ばざる「妙」なる はたらきをもたれた
みほとけの説く「法(真理)」を、蓮の華「蓮華」が持つ 三つの徳に例えた「経」です。
蓮の華の三つの徳
泥中から生じるとも染まらず(汚泥不染=おでいふぜん)
花ひらくことで果実を生じるのではなく 花のつぼみと一緒に果実が生じ( 花果同時=かかどうじ)
花ひらくと必ず実を結び、何百年経とうとも必ず発芽する(種子不失=しゅしふしつ)
の三つの徳を言う。
*空海(お大師さま)は 「観音経」を重視されていたので、高野山では日に一回はお唱えます。

観音経はすべての宗派を超え唱えることができる・・・
観音経は真言宗・天台宗・禅宗・日蓮宗はもちろん、浄土宗・浄土真宗等の浄土教を柱としての
阿弥陀如来を御本尊とする宗派にも通じる経典です。
何故なら、阿弥陀三尊来迎図には阿弥陀如来を「中尊」とし、その左右に左脇侍の観音菩薩と、
右脇侍の勢至菩薩を従え、浄土・極楽往生を願う人たちすべてを、迎え入れに来られる姿が
描かれています。
よって、観音さまは宗派を超えた菩薩で「観音経」はすべての宗派に通ずる経典です。
先日、親しくしていただいた方の開眼法要をさせていただきました。
最初に、広い居間で皆さんと観音経・偈 他をお唱えして、そのあと近くの墓地で私が10分ほどの
経を唱える間に、ひ孫さんたちに幕を取りはずしてもらいました。
亡くなられた方は「千の風になつて」の歌手・秋川雅史さんに「すばらしい歌詞をすばらしい声で
歌われているのを感動しました」と手紙を出すと、直筆の返信が送られてきたそうです。
なので私は「観音経の中に遊於娑婆世界(ゆうおしゃばせかい)という言葉があります。
これは観音さまは風のごとく自由自在に私たちの傍におられますという意味です。
ですからここに来られて、ご主人であり、父であり、おじいちゃんである○○さんを偲ばれたとき
○○さんは観音さまと一緒に微笑んでいますよ」とお話ししました。
奥さんは目を潤ませておられました。
  
2017年、大阪府吹田市・メイシァターに出展した截金(きりかね)装飾の白衣観音です。
総高70㎝。ネットで截金(きりかね)を検索して見てください。素晴らしい技法ですよ。
「一峰庵・式次第」の中に、父母の恩がいかに深く重いものかを書き示した
「略・父母恩重経」を綴りました。
「母は観世音菩薩 あなたが今あるのは 母と父があってのことです 母の胎内にあなたの命が
芽生え およそ十ヶ月 あなたの鼓動に父も喜び あなたを慈しむことを忘れたことは ありません
そしてあなたのうぶ声を聞き ふところに抱く 母のまなざしこそ 観世音(観音さま)の心です。
生まれてのち あなたは乳房をもとめ 母のふところにあまえ 母の膝に遊び 母の香りに安らぎ
育ちゆくのです 母の姿をもとめ 泣き声をあげ 母を見つけたあなたは からだ全体で喜びを
あらわし 育ちゆくのです。
ケガや病気に遭ったとき 母は あたたかい手当てをほどこし 「もうだいじょうぶよ」の声をかけ、
その声に安堵して育ちゆくのです。
あなたが成長し どんなに遠く暮らそうとも あなたの姿 音声を観じ 自在に歩みより
あなたを助け 母は喜び悲しみをともにするのです そして年老いてもなお命あるかぎり
あなたを忘れることはありません 。母の相(すがた)を観音さまと仰ぎ 朝に夕べに念じ奉ります」
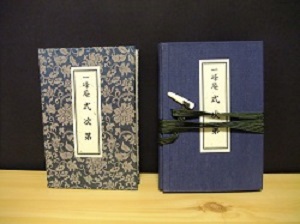
京都の和綴じ店で作ってもらいました。
市販の経典を一字一字、ワードで打ちながら一年かけて編集した私だけの式次第です。
内容は
引導・開眼・納骨作法。仏壇勤行。年回忌作法。観音経。十句観音経。略・父母恩重経。
般若心経。舎利礼。阿弥陀如来根本陀羅尼。お念仏。理趣経より百字の偈。大師法号。
光明真言。大隋求菩薩真言。大金剛輪陀羅尼。譜供養。三力。懺悔随喜。不動略念誦法。
次回はダンマ パダです
ページのご案内
|