| ビハーラ活動 2002年、初孫の成長を願って彫刻しました。 「これは坂本さんの顔ですね」と先生に褒めて?いただきました。 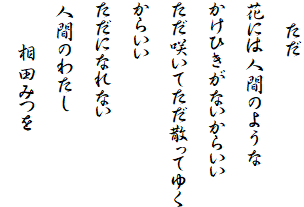 *仏教の目指すところは「己のことはさておき、すべての人々が幸せになること」です。 悟りだの、戒律だの、戒名だのは、仏教の祖・お釈迦さまが亡くなられてからの 後々の人たちが、屁理屈をこねて考え出したものにすぎません。 ビハーラ活動・・・ 「ビハーラ」という言葉はあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、 この言葉は古代インドのサンスクリット語のViharaをそのまま音訳したものです。 そのビハーラという言葉は、「精舎・僧院」「身心の安らぎ・くつろぎ」「休息の場所」を 意味しています・・・ネットより 恵まれない子供たちに食事、言葉がけをしている若い人の活動に賛同して、 わずかながら夫婦で毎月の寄附をさせていただいています。 その人たちの活動報告をメールで受け取るたび只々、頭が下がります。 これこそ真の菩薩であり、大乗仏教の説くところの利他行=菩薩行です。 仏教がもともと課題としてきたのは、命をうけて生まれでたときから始まる 老・病・死の苦悩に応えることである。 大乗仏教に於いての寺は、医療・介護といった社会福祉の各分野と共に 今そこに、親の愛情もうけることなく虐げられている子供たちを受け入れ、 その子らに心身の安らぎ・くつろぎを与える処であり、言葉がけをするのが僧侶です。 それを実践することが「ビハーラ活動」と呼ばれるのです。 それを実践している寺・僧侶は如何ほど存在するのか? 人が死んでからでないと携わることしか出来ないのが寺という処でしょうか? 寺院の固定資産税を担っている人々の日々における苦しみを真摯に受け止め、 寄り添う処が寺としての役目で有り、それを実践できないのなら、 既に寺ではありません。 また、得意げに仏教教義(狭義)は垂れるが、葬式・死後の行事しか出来ない、 しない僧侶は僧侶という存在者なのでしょうか? 仏教の説くところは「忘れなさい=無執着」であって、年回忌等は仏教教義には ありません。 「くどくどちまちまと余計な細かいことを考へ、あれこれいじってミソをつけるな」 祖父・江戸幕府8代将軍・徳川吉宗の享保の改革を手本に寛政の改革を行い、 幕政再建を目指した松平定信の言葉。 次回は長崎・出島〜天草・富岡城を訪ねてです ページのご案内 |